Amazonプライムビデオで、11/8から映画版ルックバックが配信されました。
私は、上映期間中に映画館に足を運びたいと思っていたのですが、結局行けずに終わってしまったことを後悔していました。
原作である漫画の方はすでに読んでいて、色々と感じるところがありすぎて一言で好きと言っていいのかも分かりませんでしたが、心を動かされたのは確かです。
思い入れがある分、映画版を見るのは楽しみでもありわずかに不安でもありました。
しかし結論、とても丁寧に作られていて、皆が絶賛していた意味がわかり、嬉しかったです。
※以下、ストーリーの内容に触れる感想となりますので、ネタバレを避けたい方は読まないようにお願いします。
「背中」の意味を考える
タイトルのルックバックという意味は、作中にも出てくるように「背中を見て」と直訳することもできますが、調べると別の意味がいくつも出てきます。
- 回想する、振り返る
- 尻込みする、後退する、うまくいかなくなる
主にこの二つに分類できるのではないでしょうか。
これは主人公の藤野が、京本を失った後に感じたことと無関係ではないでしょう。
作中に出てくるいくつもの背中。
- 藤野がサインした京本の背中(死後も残り、藤野が追いかける京本の背中)
- 変わらない小さな部屋で、机に向かい続けた作家としての直向きな背中
- 京本が成長する過程で追いかけた藤野の背中
- 物語後半のIFの世界で京本によって書かれた4コマ漫画の「背中を見て」
- 背中から刺される(=裏切り)かのような一連の出来事(運命からの裏切りとも取れる)
- 京本と別の道を選んだ後、無機質に時間の経過だけを示すような単行本の背中(背表紙)
このように作中で、背中で語られていることがあまりにも多いです。
タイトルも含め、これだけの場面と絡められるのにまず面白さがありました。
個人的な感想としては、藤野と京本が出会い、そしてすれ違って、背中あわせに別の道を歩き出したあと、藤野が失った京本を振り返り、その追憶の中の背中を見てまた歩き出す——。
そんな物語なのではないかと感じました。
「扉」の意味を考える
背中ほどではないですが、作中は「扉」もとても意図的に描かれているように思えます。
- 四コマ漫画がすり抜け、2人を出会わせた京本の部屋の扉
- 京本が事件の犯人に襲われる時、色をつけていた作品の扉
扉は、2人の人生が大きく動いて次の物語に移行する「入口」としてのメタファーでもあり、人生に立ちはだかる「困難」ともかかっているのではないかと思います。
作品が伝えたかったことを自分なりに考察してみる
藤野は、京本を失ったきっかけを自分が作ってしまったと悔やみます。
「何で描いたんだろ…」「描いても何も役にたたないのに……」
これは、絵や漫画だけでなく、何かを作った経験のある人なら誰もが思うことかもしれません。
それでやめてしまう人もいれば、続ける人もいる。最終的に、藤野は後者でした。
物語後半では、京本が助かるIFの世界が描かれています。
藤野と出会わなくても、京本は自ら外の世界に出て行ったし、京本を犯人の魔の手から救ったのは藤野が姉に勧められて続けていた空手で、物理的なパワーでした。決して漫画ではなかった。
あれだけ直向きに向き合い続けた藤野の創作は、部屋から「出てこないで!」と願っても、この点において無力でした。
藤野が最も真剣に向き合い続け、京本とつながるきっかけとなった漫画では、大切な友人を直接的には救えず、運命を大きく変えることはできなかった。
ここで、決して創作が無意味で無力だと、私は言いたくはありませんし、作品もそう入っていないと思います。
2人で見た夢が楽しかったのも、雨の中を飛び跳ねるほどの歓喜も、創作があったからです。そして、孤独な戦いで、読んでいるだけの方が楽しくて、何の役にもたたないとわかっていながら辞められない——それこそが、理由のない魅力に取り憑かれているということなのでしょう。
作品が伝えているのは、あらゆる創作活動が無力で、孤独で、それでも辞められないということなのではないでしょうか。
余談、感想
今回、ルックバックを見ていて少し思い出した作品がありました。
私の好きな漫画で、ヤマシタトモコさんの「違国日記」。
登場人物の小説家は、苦しみながら創作を続けていますが、姪である主人公に「才能」について尋ねられます。
小説家である叔母は、「やめられないこと」と答えます。
「私よりおもしろいものを書く人にやめる理由が訪れて、私にはないのを…わたしはわたしの才能だと思うことにした」と続けるのです。
ルックバックにも、そんな「才能」を感じずにはいられませんでした。
藤野が、1人になっても、ただ書き続ける背中には、胸が締め付けられます。
孤独を埋めるために創作するのか、創作するほどに孤独なのか。
私には分かりませんが、そう言ったことについて考えさせられる素晴らしい作品でした。
そんな痛みも伴う創作に携わる全ての人、特に作品の題材となっている物語制作に関わる人たちに、敬意を払うようなエンドロールも映画ならではの演出だと思いました。


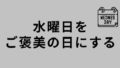
コメント